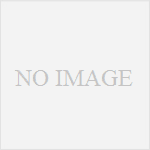一般
- 盗難車に別の車のナンバー 会社社長逮捕 暴力団員らに販売か | NHK | 事件
- 宮城県大郷町の議会解散問う住民投票手続きを一時停止 仙台地裁「署名無効」 – 産経ニュース
- 東北新幹線内の乗客やけどで会社役員2人に罰金50万円 硫酸漏えい罪で仙台簡裁 – 産経ニュース
ゲーム
- カバー、任天堂からの要請を受けガイドライン違反疑惑のゲーム配信対応を発表 – GAME Watch
ああ、動画は見ていないけど、ゲーム関連の話題として目には入っていた。
ゲームデータを改造したものと思われるものでプレイしてしまっているのではないかという疑惑があった件のか。
いわゆる「違法ROM」とか「改造ROM」とか言われるものですね。
ちなみにここで言うROMってのは、「Read Only Memory」のことです。
「読み取り専用」の記録(メモリ)を意味して、日本だとゲームのカセット・カードリッジのことをROMカセットって呼んでいたり、
あとは一般的に(言葉が)使われているのは、CD-ROMとかDVD-ROMとかのROMも同じ意味です(この場合、書き込みができない読み取り専用のCDやDVDっていう意味)。
まぁ、ゲーム関連の話題でROM(ロム)っていう言葉が出たときは、
回り回ってゲームデータのことを指すようになってしまっている、っていう認識で良いとは思います。
関連:Read only memory – Wikipedia
関連例:ロムカセット – Wikipedia
個人間売買(メルカリなど)とか、あるいは中古ショップとかでも、
該当のカセットが流通してしまっている可能性はあって、それを知らないまま購入してプレイしてしまう可能性はありえる。
だからその事実だけだと買った本人のせいとは言えない状況だけれど、
でもゲーム配信となってくると権利問題としてプレイ・配信している側に責任は出てくるから、
それが問題のあるデータとは知らなかったとしても、疑いが出たら まず公開は止めるべきではありますね。
(脱線するけど、ゲーム関連でもネトゲー(オンラインゲーム)や掲示板とかで使う「ROM」の場合はたいてい別の意味になります。
その場合は「Read Only Member」のことを指していて、「読むだけの人」、つまり書き込みや発言をしない人や状況を指します。
例えばゲーム中に電話とかがきて、ログインはしているけど発言はできないときに、「ちょっとROMします」とかの表現で、状況を伝えることがあったりする
(今の時代だとWeb会議中に使う人もいますね)。
で、回り回って、離席することを「ROM」って言うことがあるんだけれど、これは使い方として間違いです。
ROMは「読める状況」だから席は離れていないので。
ネトゲー界隈だと、席を離れる場合は「AFK」を使うのが一般的だろうか。
AFKは「Away From Keyboard」の略で、キーボードから離れていますって意味で離席を指している。
20年以上前、もともとネトゲーをパソコンでプレイするのが一般的だった時代に、海外文化圏から日本に入ってきた言葉です。
だから「キーボード」がない環境で離席するときにAFKを使うのは、本来はおかしな表現ではあるのですが、
いつの間にか環境に関わらずネトゲー全般で使われることがある言葉になってますね。
まぁゲームのことをファミコンって呼んだり、モバイルバッテリーのことをモバブって呼んだり、
言葉の意味の使い方が別の関連の指している言葉で上書きされることがあちこちで起こることがあるので、
日本は正確な言葉・文字の意味にあまり こだわりがないのかもしれませんね。
SNSのXのことをいつまでもTwitterと呼んでいたり、動画の再生関連で「巻き戻し」っていう表現を
今も使う人がいたりするのも、括りとしてはある意味 同じかもな。
この場合はあくまで「旧称」として定着していたものだから致し方ない部分はあるけども。
そもそも、例えば第一人称を指す言葉・表現がたくさんあるくらいだからなぁ。
「私、我、吾輩、儂、俺、僕、自分、etc…」と、文化として昔から表現が寛容な部分はありそうだ。
(日本語を学ぼうとしている人からすれば、このうえなく厄介でしょうが。。)
と、脱線しすぎたか。)
ガジェット・サービス・ツール等
- 「Google Pixel 9a」国内向けに16日から発売 約8万円~ – ケータイ Watch
- Lexarが1TBの「microSDXC Express」カードを告知 – デジカメ Watch
一昨日(4/7)付けでピックアップした海外で発売したやつですね。日本でも展開するようで。
- Instagram、保護者の許可なしにライブ配信させず 13~15歳を保護する新機能を導入 – ITmedia Mobile
技術・事業・セキュリティ等
- 米セキュリティ研究者が“謎の失踪” 大学Webサイトから情報抹消、FBIも自宅捜索 中国の助成金が関係か:この頃、セキュリティ界隈で – ITmedia NEWS
- システム障害想定のマニュアル整備せず 中日本高速社長が謝罪 | 毎日新聞
ううむ、しかしまだ原因が特定できていないのか。
ひょっとして、例えばブラックホールルーターみたいな、潜在的な問題が、改修きっかけで表面化したとかなんですかねぇ。
それだと改修自体が悪いわけじゃないけど、なかなか稀有な状況で、
たまたま今まで正常に動いていたシステムに、突然トラブルが発生するようなことになるってのは、本当に稀なケースだけどあるからなぁ。
(例えで出したブラックホールルーターの場合だと、システム(プログラム)改修によりデータ長が変わって、それがきっかけで、たまたま今まで正常に動いていたボーダーラインを超えて、
ルーターが通信データを破棄するようになってしまい、システムに正常にデータが届かなくなって突然不具合が出るようになる、みたいな感じ。
この場合、プログラムが動いているシステム側には一切 非が無くて、通信インフラ側の問題だから、
この辺マジで、IT系の「プロ」だとしても、担当区域や分野が異なるからそこまで影響を把握しきれない、あるいは失念していたりする部分があって、原因特定まで時間がかかる。
だって、テスト・開発環境と本番環境だと使う通信インフラ=ネットワーク環境、使用しているネットワーク機器までが完全に同一っていう保証はまずないですからね。
そのせいで、テスト・開発環境では何をどうやっても問題が発生しないのに、本番環境だけ発生するっていうケースも中にはある。)
そういう厄介なケースはさておいても、インフラ系の問題は実際に問題が出るまでは見逃しがちかもなぁ。
あとは似たようなケースでプログラム(自分たちが作ったものか、第三者のものかは限らず)の潜在バグの可能性とかも普通にありますけどね。
例えばメモリを不正に操作・破壊する系のバグとかも、やっぱりたまたま正常に動き続けてしまうことはあるからな。
でもこっちは前述の例のケースよりかは原因は特定しやすいとは思う。まぁ第三者のものがきっかけだと厄介だけども。
いずれにせよ、例として挙げていないものも含め、発生・遭遇率は低いものでも可能性は色々ある。だから特定に時間がかかってるのかもしれませんね。
そして原因が究明できないと再発する可能性が否定できないから、頑張ってもらうしかない。
しかし結構大きい、利用者がいるシステムなのに、障害マニュアルの整備もされていないっていう、
なんだか不安な運用をしているようだから、単純なバグも見落としているんじゃ、っていう、正直 偏見が生まれる部分があるのも否めないところだ。 - 「さすがに人格批判では」出してた論文が査読に10ヶ月ほど待たされた後、「stupid」と書かれてリジェクトされました – Togetter [トゥギャッター]