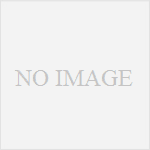一般
- 豪で16歳未満のSMS利用禁止 12月10日から禁止措置施行(AP通信) – Yahoo!ニュース
- 公用PCで芸能記事など457時間閲覧 停職・給与128万円返納 [佐賀県]:朝日新聞
- 旅行の予定をSNSにアップしたら、誰かに勝手にキャンセルされていた─個人情報の管理に注意(クーリエ・ジャポン) – Yahoo!ニュース
- 給食ウズラで小1窒息死 みやま市側は争う姿勢 福岡地裁支部初弁論 | 毎日新聞
関連:給食のウズラの卵で小1児童が窒息死した事件、遺族が市に損害賠償を請求「悲しみはわかるけどよく噛んで食べるのは家庭で教えることでは…」と疑問の声 – Togetter
いや、当初は自分も保育園・幼稚園じゃないんだから、小学校で食に関する指導なんてするのかよ・・・って思ったんですが
(事実、自分は給食で何か指導的なことを受けた記憶が正直無いどころか、給食中に先生がいないことも ままあったしな)、
あくまで「主観」でそう思っただけで根拠なんてもちろんないので、法律に基づいてこの辺について少し調べたら、
下記関連などを追ってみる限りだと、いやはやこれ、学校の責任が確かに出てくるんじゃないだろうか、と、考えを改めました。
関連:学校給食の役割!教員が知っておくべきその目的やねらいとは?│edulo.jp
まず、給食の時間は、教師にとっては休み時間ではなく、「授業」として位置づけられているとのこと。つまり給食における教師の職務は確かに存在する。
具体的には、って部分を以降つらつらと記載する。なお、各種関連はきっちりとは読んでないです。時間的都合もあったので かなり流し読み。
学校給食法における原文で、まず重要だろうと思った部分は下記。
関連:学校給食法 | e-Gov 法令検索
第一章 総則
(略)
(学校給食の目標)
第二条 学校給食を実施するに当たつては、義務教育諸学校における教育の目的を実現するために、次に掲げる目標が達成されるよう努めなければならない。
(略)
二 日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと。第三章 学校給食を活用した食に関する指導
第十条 栄養教諭は、児童又は生徒が健全な食生活を自ら営むことができる知識及び態度を養うため、学校給食において摂取する食品と健康の保持増進との関連性についての指導、食に関して特別の配慮を必要とする児童又は生徒に対する個別的な指導その他の学校給食を活用した食に関する実践的な指導を行うものとする。
(略)
3 栄養教諭以外の学校給食栄養管理者は、栄養教諭に準じて、第一項前段の指導を行うよう努めるものとする。
この場合においては、同項後段及び前項の規定を準用する。とまぁ、食事についての指導を行うものだと、きっちりと法律で定義されているんですよね。
ただ、指導をするのは「栄養教諭」や「学校給食栄養管理者」と書かれている。
学校給食栄養管理者については第二章に定義があるが、「栄養教諭」については突然出てくる単語な上にこの法律内での説明も特にないので、自分のような無知な人が見るとこれが何なのか分からない。
第二章 学校給食の実施に関する基本的な事項
(略)
(学校給食栄養管理者)
第七条 義務教育諸学校又は共同調理場において学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員(第十条第三項において「学校給食栄養管理者」という。)は、
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第二項に規定する栄養教諭の免許状を有する者又は栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項の栄養士
若しくは同条第三項の管理栄養士の免許を有する者で学校給食の実施に必要な知識若しくは経験を有するものでなければならない。教育職員免許法に栄養教諭の規定があるらしいので、一種の資格なんだろうと、別途で検索した関連は下記。
関連:栄養教諭ってどんな仕事? 職場での役割・必要な免許は? | なるほど!ジョブメドレー
これらの書き方から想像するに、クラスの担当教諭が担っている役割ではなさそう。
だがしかし、そもそも給食の管理や計画をするような立ち位置の人は、学校の中でもそう何人も配置されている存在ではないだろうとは想定できて、
担当者の数がいない=学校内の全クラスの給食中の「監視や指導は物理的に無理」じゃん?
なのに、給食法では指導しろって無茶ぶりしているけど、
この辺、いったいぜんたい どういう運用にしろっていうんだろう、と 疑問に思ったので
少し探してみたら下記関連でまさにこれに関するド直球なQ&Aがあった。
関連:学校保健、学校給食、食育:文部科学省
この関連内の「学校給食・食育」の「栄養教諭」にある下記のPDF。
関連:食育・栄養教諭に関してよくある質問Q&A(平成30年)(PDF:622KB)
Q6. 栄養教諭は、学校給食の管理業務を行うだけでも大変なのに、複数の学校を担当している状況で、実際のところ、さらに食に関する指導は、無理ではないですか。
A6.食育の推進は、学校全体の教育活動によりなされるべきものです。
栄養教諭の職務は、教職員各々の専門性を生かしつつ、相互の連携協力の下に全体的な食に関する指導がなされる体制をつくりあげることが第一義的に求められるものです。
その上で、児童生徒に対する指導として自ら担うべき業務を分担することが求められるのであり、栄養教諭の勤務時間に占める児童生徒に対する教育指導の時間の占める割合が高くないということ自体が、栄養教諭の職責を果たしていないということにはなりません。
また、栄養教諭が学校給食の管理業務を担っていることが、食に関する指導を行う上で、むしろ大きな利点となるといえます。文部科学省の回答ではざっくりいうと、管理者だけじゃなくて、学校全体の教育活動であり、教職員たちと連携協力して役割分担してやっていけよ、と、そうあるわけです。
クラスの担当教諭における、給食という授業の職務はまさにこの辺を担うものなんだろう。
(でもこれ、冒頭の括弧内にさらっと書いたけど、自分が小学生の頃、給食時間中に先生がいないことも ままあったってことを考えると、
学校や担当教諭がそもそも給食における上記の役割を認識していないんじゃ? と思うのだが・・・。
ああ、いや、自分が小学生の頃と上記についてはもしかすると途中で法改正とかそういう類があった場合は何とも言えないか。そこまではさすがに調べてない。
少なくとも今は、上記の運用の「ハズ」だとすると今回の事案については、自分の小学生の頃の感覚は切り捨てて考えた方が良さそうだ。)
だとすると・・・、という部分で、冒頭に書いた通り、これ、学校も含めて、食に関する指導の責任はあるんじゃ? との考えになるわけです。
まぁこれはこれで具体的にどこの部分、誰が責任を追うんだろうっていう話になりますけども。連携協力するものなら、やっぱり責任も連帯するもの? と素人考えにはある。
ただ当然、学校側が100%というわけでもなく、各家庭でのしつけもあるでしょう。
この辺、責任自体が認められた場合は、裁判で責任の範疇についての結論は出るとは思うし、
一方でそもそも責任がないとなった場合、上記の法律はじゃあなんなんだと、法整備なり諸々の明確化なりはしなきゃいけなくなるだろうから、
どういう決着になったとしても先行きが気になるところです。
ガジェット・サービス・ツール等
- ゆうパック「動物」発送禁止に…爬虫類認めていたら不正続出、「ミーアキャットが死んで届いた」例も : 読売新聞
- すべてのWindows 11搭載PC、「Hey Copilot」でAI起動が可能に 「Copilot Vision」も利用可能 – ITmedia NEWS