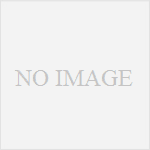一般
- 生徒会長に10万円交付、元手に公約実現を…「主体的な課題解決」期待 : 読売新聞
- バナナボート転覆、男性死亡 北海道・小樽の海水浴場 | NEWSjp
- 「全ての野良犬を収容せよ」 インド最高裁、狂犬病対策で | NEWSjp
内容の是非やら、こういうのをどこまで裁判所が決めるのかとか、
決めたとて方法は丸投げって部分もそうだけど、
国によるところではあるが、なんか色々なところで考えさせるな。 - 大量のポテトやバーガーが捨てられ…ポケモンカードが抜かれたマクドナルドのハッピーセットが廃棄され“路上無料配布”も(FNNプライムオンライン(フジテレビ系)) – Yahoo!ニュース
技術・事業・セキュリティ等
その他
- 最近やったゲームの駄文
ここのところはSteam版の積みゲー消化に注力していた。
具体的にはファイナルファンタジー8、クロノ・トリガー、ドラゴンクエスト11S、ファイナルファンタジー10と10-2をクリア。全部スクエニのゲームですね。
FF10-2を除けば、もともと別のプラットフォーム(別のゲーム機)ではクリア済みなので実質的には再プレイみたいなもの(Steam版としては初プレイだけど中身は同じだし)。
思い出補正って強いんだなとは思ったな。クロノ・トリガーとか、こんなに世界狭かったっけ、行けるところ少なかったっけ、とか、FF10もここまで一本道で何もできない内容だったっけかなぁ・・・となった。
それなりに最近はゼノブレイドクロスDEなり、オープンワールドなゲームをやってたから余計に狭く、要素が少なく感じた部分はあるとは思うけども。
実質 再プレイではない例外としてファイナルファンタジー10-2(FF10-2)は、ノーマル、ティーダ復活、クリーチャーエンディングをちゃんと見たくらいには やり込んだ。
FF10-2をやり込んだ理由は、無印版(PS2)は持ってはいるけど積んだまま未プレイで、リマスターのPS Vita版でちょっとはプレイしたけど途中で止めちゃっていたので、今回まともにプレイ&クリアしたのが初めてだったから。

Steam版だといわゆる公式チートで、F1キーで倍速(等倍、2倍、4倍モード。クリーチャーでの戦闘中は4倍速でもいいが、さすがに4倍速だと 移動ではうまく向きが調整しづらくなり話しかけたり調べたりするのには難が出るため通常時は2倍速がオススメ)、F2キーで強化(戦闘中、自動蘇生は無理だがHP,MPが減ると自動回復しつづける。即死級の方法以外では死ななくなるし魔法等も使いまくれるので、戦闘にコダワリがなければ有効化するのを特にオススメ)、F3キーでエンカウント通常・増加・オフ(このエンカウントOFFはさすがに強制エンカウントは防げないけど、ベベル廟の100階層攻略なんかもボス戦やトンベリのシンボルエンカウント以外は完全にOFFれる)などができる(F4キーはオートバトルON・OFF。使ってないから挙動不明だけどクリーチャーの自動戦闘のことではなくメイン3人の行動だとは思う)。
あとは、ESCキーを押すともろもろのメニューが出てくる中で(ちなみにF1キーとかの機能もこのメニューからも実行はできる)、なんていう名前の項目だったかは忘れたけど、データの改造も公式に用意されています(例えば全アビリティ習得、アイテム所持とか、お金を最大にするとかが出来る)。ただしこっちの改造機能については使うと実績が獲得できなくなるケースがあるので自分は使いませんでした(前述のF1~キーとかは使っても実績に影響はない。なお、厳密に言うと先にFF8でプレイしていたとき、お金だけ最大にするのを使ったら、案の定 お金とか無関係に あらゆる実績が獲得できなくなったので、FF10シリーズではデータ自体を改造する機能の方は使わないようにした)。
この辺の機能は、FF10とか、FF8とか他のスクエニのその辺のFFシリーズでは用意されているから、単純にクリアしたいだけならSteam版だとかなりゆるく安全にプレイできます(特に有効化しても実績の獲得には影響しない、戦闘中の自動回復ができるF2キーがとにかく便利)。
とはいえそんな機能があるというのに、FF10-2に至っては、実績(トロフィー)を見る限り、少なくともSteam版でまともにプレイしているユーザー、かなり少ないみたいですね。
例えば、ティーダ(前作FF10の主人公)復活の条件が満たされるコンプリート率100%の「完全制覇」という実績は、Steam版での達成率は現時点(2025年8月9日)では1.3%のプレイヤーだけ。
で、ある程度ミッションを順番にもらさずやっていけば比較的達成しやすい、「一つのエピソード完了」っていう実績ですら4.0%。
やり込みの中でも達成条件がゆるく達成しやすい「交渉上手」(わいろを30回使用。※成功する必要はない)に至っては1.1%という、まさかの「完全制覇」よりも達成者が少ないことから、少なくともSteam版ではまともに やり込んでいるユーザーがほぼいないってことがよくわかる数値でした。
いや、この辺、実際にプレイしたら感じるけど、FF10-2はなんかユーザーが求める方向性と違うというか、やり込みが色々と大変&面倒だったので、こういう数値になっているのはなんだか納得してしまいます。
自分の場合はエンディングを迎えても感動とかより、やっと終われたっていう疲労感が強かったですから(ストーリー本編自体は長くはないんですけどね)。
できれば後日譚の、FF10シリーズの完結編となるFF10-2 ラストミッションのプレイも着手したかったけど、今のところ保留にしてます(なによりラストミッションは風来のシレンみたいなダンジョンRPGでFF10-2とはシステムが別物になるので、そっち系のジャンルを好まない自分だとプレイ意欲が湧きづらい)。
あとは花札の虎っていうインディーズゲームだろうか、これの体験版もプレイした。文字通り、花札のゲームです。
同じ発売日(2025年7月31日)に、同じジャンルのホロの花札っていうVTuberのファン層が多いゲームが発売されたので、花札系のゲームではそっちの方が注目されていたけど、
Steam版でどちらの体験版もやった限りだと、ひたすら花札(こいこい)をしたい自分みたいなユーザーとしては、
花札の虎の方が個人的には好みだった(が、どうせ積みゲーを増やすだけになっちゃうので買ってはいない。タイミングがあれば買うかも、程度)。
まぁハクスラ要素があって、なんていうか札の改造が出来てしまうから、例えば短冊にカスの効果も付与したり、たった1枚で猪鹿蝶とか、花見に一杯・月見に一杯とかを実現できるようになったり、やり込んでいくと揃えられる役が多くなって、点数がインフレ化していきます。
そして対戦相手にはHPのようなものが設定されていて、花札自体の勝負に勝ったとしてもそれ(HPのようなもの)を減らしきれないと次の対戦には進めないので(HPを減らしきるまで同じ相手と再度対戦(限度はある)か、対戦自体リセットして最初の対戦者からのプレイ=過程で達成したアチーブメントのようなものの効果が反映されるメリットはあるので、途中で勝てなくても、少しずつでも札の効果を強めるため周回プレイすることに意味はあります)、勝つことは大前提として点数を稼ぐことも戦略として必要になってきます(相手のHPもインフレ化する)。
そういう意味だと最初は普通の花札のように遊べても、徐々にゲーム性の高い「花札のような何か」に変わって行ってはしまう。その点では純粋に花札として楽しめなくなる可能性は出てきます。
ちなみに自分がやったのは最新版の体験版ではないし(7/19時点)、体験版でできる範疇の内容に留まるけど、その時点でも下記みたいな点数は叩きだせた。

普通に花札(こいこい)で1勝負するくらいの点数だったら10点を超えるのだって十分ですからね。
この画像のように7,652,736点ってなんだよって話ですが、これでもまだまだ上は目指せる。
そもそも こいこい の場合、役を揃えても、続行するか止めるかを役を揃えた人が決めることができて、
そのまま続行した場合、さらなる役を揃えることでより点数を高めることを狙えるってのが特徴です。
(こいこい の場合、花札の細かい種類を覚える必要がないってのも利点だな。何の花だとか何月に属するとかそんなのを覚えなくていい。単純に札の図柄で判別できる種類と役の組み合わせだけ覚えれば遊べるという、だいたいはトランプで言うポーカーと同じような感覚でいい。まぁ初見では少し分かりにくい図柄の札もありますけど、そこは慣れだな)
続行については「勝負を継続だ、かかって来い!」みたいな感じで「来い!来い!」って覚えればいいですかね。
ただし、続行した場合、相手か自分が新たな役を揃えるまでプレイを続ける必要があり、
もしその後、どちらも役を揃えられなかったら引き分けになってしまうし(トランプと同じで札の種類と枚数は決まってますから、このパターンは割とあります。場に出ている札・枚数から推測し、まだ出ていないと思われる札で新たな役が作れるのか見極めが必要)、
最初に自分が役を揃えて続行を決めても、次に役を揃えたのが相手だった場合は相手方の勝ちになりえてしまう(その時その相手も、続行するか止めるかを選択する。そこで止めたら相手の勝ち、続行したらまた新たな役が出来るまで勝者未定)という取引も面白いところです。
そういった特徴から、逆に言うと・・・いや、これはほとんどのゲームに言えることではあるけれど、負けなければ何点だろうが勝ちは勝ちで、とにかく先に勝ち越して全勝すれば点数は無意味になります。
点数はあくまで、複数回勝負で勝者が入り混じった場合に、最終的に総合点が高かった方が勝ちになるというための材料ですね。
(あるいは、勝負に負けている人が、高得点で一発逆転を狙うか・・・だけど、札の種類・数に限界がある以上、揃えられる役も限界があるから ある程度の点差がつくと逆転は不可になります。相手方が低い点数で勝ち越している場合のみ、逆転の望みがあるくらいか)
でもこのゲームだと前述のようにHPのような仕様があるため、勝負に勝っているだけじゃ相手を倒せないっていう、花札のゲーム性を良い感じにアレンジした面白い内容だなぁという印象でした。
なお、ホロの花札の方は、そういったゲーム性のそのもののアレンジはないので純粋に花札で勝負するって感じの内容ですね(花札に関係ない要素もありますが、そういった要素は自分の評価外です)。
ただ、ルールの変更はできて、通常のこいこいのルールも選べますが、それに加えてホロの花札だけの特殊なルールも選べて、
その場合は本来の花札の種類とは別に付与される札の特性も加味する必要があり、標準にはない新たな役の追加で点数加算も狙えるので、
通常ルールだったら負けていたケースでも特殊ルールで追加された役を揃えることで勝てることも出てきたりするってのが、アレンジ部分としては面白い所だとは思います。
なので、勝負を楽しみたいならホロの花札、ゲーム性を楽しみたいなら花札の虎って感じの住み分けかなぁ。
個人的には標準のルールで、ただひたすら こいこい で勝負し続けたいだけ、他の要素は邪魔になるから入れないで欲しいので、どちらのゲームも理想というわけではないんですけどね(例えばサクラ大戦シリーズのミニゲームにあった花札はまさにその仕様で、自分は本編より遊んだくらいだ)。
とはいえ、ゲームとして考えれば、どちらの作品もそれ相応に楽しめて嫌いじゃないので、花札に特化したゲームは数が少ないだけに選択肢としては歓迎しています(でも前述したけど、買うかどうかは別。タイミング等があるからな)。